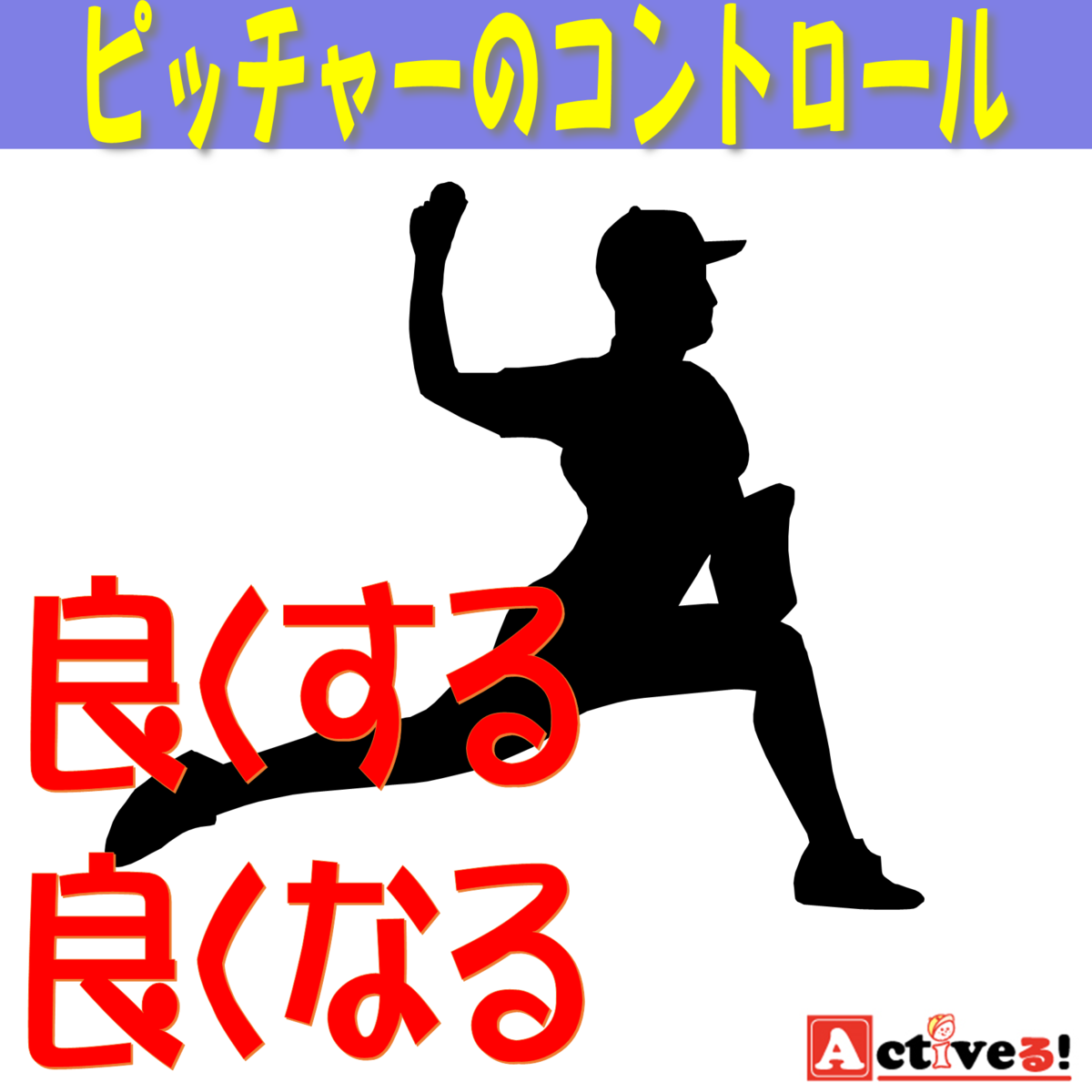
ピッチャーのコントロールを良くする3つの方法とは?【野球上達ガイド】
ピッチャーでコントロールを良くしたい、あるいは良くなりたいという選手は多いことと思います。ピッチャーがまず求められる能力がコントロール…制球力なのですが、ここでいくつかの方法を紹介します。これらの方法で、コントロールの良い安定感のある投手を目指しましょう。
Writer
公式ライター Activel_director
ピッチャーに求められるコントロールとは?
野球の投手の制球力は、先天的なものもあるかもしれませんが、より正確性を増し、チームのエースとして力を発揮するためには様々な練習やトレーニングが必要となります。コントロールは良くなるものですし、良くすることができますので、様々な方法を通じて上達を図りましょう。
野球のワンプレイはピッチャーの投球で始まる
ストライクの割合が低く、コントロールが悪いピッチャーは、制球難だったりノーコンと呼ばれ、決してチームに良い影響を与えることはできません。コントロールを良くすることで、ストライクを投げ込んでいけば、味方守備陣にも良いリズム感でプレイさせることができます。
ピッチャーのコントロールが良くなる方法①
その一つは、野球は基本的に屋外で行うスポーツであり、試合をするグラウンドも毎回同じではないので、天候や温湿度、グラウンドの状態やマウンドの高さなど周囲の環境に合わせる能力も必要ですし、体調や疲労度といった試合の経過に伴う自分自身の変化にも対応し、調整を図らなくてはなりません。
様々な環境や変化に対応していく方法の土台となるのが、投球フォームを安定させることとなります。
投球フォームを安定させる
ピッチャー コントロールを良くするために大切にして欲しいこと
【4つのフォーム】
オーバースロー
スリークオーター
サイドスロー
アンダースロー
フォームの違いは、腕を振る角度ですが、ピッチャーはボークなどの違反を除けば、基本的にどのような投げ方をしてもかまいません。一球ごとに投げる腕の角度やリズムを変えてよいのです、毎球フォームを変えて投げるピッチャーはほとんどいません。
ピッチャーは、1つか2つの投球フォームで投げることが通常であり、コントロールを良くするには、自身の投球フォームがいつも変わらないことが大事となります。
投球フォーム作りで意識すること
リズム感は、左足を上げたときに、一瞬だけクッと溜めて投げるなどの方法により、投球動作が始まってからリリースしフォロースルー及びその後の守備に至るまでの流れをスムーズにおこなうことです。
また、テイクバックしたときの肘の高さや、ヒップファーストや投球動作の中での視線の置き方や踏み込む足の位置など、自身の投球フォームにおいて重要だと考える箇所をチェックポイントを設けることも重要です。
これらは、コントロールが乱れ始めたときに元に戻す場合にも有効です。
投球フォームを安定させるトレーニングメニュー
野球 シャドーピッチング 練習方法
・体幹トレーニング
・足腰の鍛錬
・シャドーピッチング
体幹トレーニングや足腰の鍛錬は、投球数が多くなってきて体力や球威が落ちてきたときでも投球フォームをブレさせず、継続してコントロールを良くするうえで必要なトレーニングです。疲れなどで腰の高さが上がってくると、必然的にリリースポイントも上がるので、やはり足腰の粘りとブレない体幹は非常に重要です。
シャドーピッチングもポピュラーなピッチャーの練習方法で、肩を消耗することなく体や腕の使い方を安定したものにしていく上で役に立ちます。
ピッチャーのコントロールが良くなる方法②
得意なコースを作る
ピッチャーはコントロールを良くするために、どんなに調子が悪くても、ここだけには投げれるというコースを作っておくと明確な軸ができます。得意なコースを作ることも、コントロールが良くなる一つの方法といえます。
得意なコースを作るうえで意識すること
バッターの外角低めは最もヒットにしづらく、ヒットになっても長打にはなりにくいコースです。右打者の外角に投げ込む練習をし、高低のコントロールを意識することで精度を高めましょう。
得意なコースを作る練習メニュー
ピッチャーマウンドのプレートの幅を有効に使ってみると、バッター目線では明らかに角度が異なり、バッターを打ち取る可能性も高くなります。球威とコースに加えて、角度も意識してトレーニングするようにして、ボール球のカウントが多くなってしまった場合でも、落ち着いて得意なコースでストライクを取れるようにしていきましょう。
ピッチャーのコントロールが良くなる方法③
自分のリリースポイントを掴む
【制球力アップ】現役大学ピッチャーによる「コントロールを良くするコツ」【投手必見】【大学ベストナイン】
コントロールが良くなるためには、自分自身の投球フォームの中でリリースポイントを微調整できる能力が必要となります。リリースポイントを掴むということは非常に重要な方法で、これは基準を作ることを意味します。
基準があることで、ズレを認識することができますし、ズレが生じた場合には戻すこともできます。野球の投手は毎回同じマウンドで投げるわけではありませんので、試合では使用するグラウンドのマウンドにマッチしたリリースポイントを早く掴むこともピッチャーに必要な能力の一つです。
リリースポイントを掴むための前提条件
①投球フォームが安定していること(一定であること)
②得意なコース(基本的にバッターが打ちづらい)コースに投げ込むリリースポイントであること
投球フォームは腕の振り(角度と速度)が一定であることが最低限の条件となります。あらゆる腕の角度と速度に応じたリリースポイントを掴むことができるのであれば支障はありませんが、難しいのが実状です。得意なコースに投げるポイントは、自分の基本となる投球フォームのリリースの基準をつくることです。これは投球術(配球)の最も基本となる球種とコースであることも重要となります。
リリースポイントを掴みやすくするイメージ
このポイントでリリースすると、このような軌道でボールが飛んでいき、キャッチャーが構えるミットに収まるというラインがはっきりとするということは、リリースポイントはもとより、ピッチャーが自分自身の持ち球や球速などをしっかりと自分のものにしている裏付けとなります。これが、コントロールを良くするためにリリースポイントを掴む上で効果的な方法だといえます。
コントロールのためだとしてもやってはいけないこと
その優位性を奪うべく、キャッチャーの配球を読んだり、ピッチャーの表情を見たりするなど、対峙するバッターは様々な方法をつかって次に来るボールの球種やコースの絞り込みを行いますが、ピッチャーはコントロールを良くするためだとしても、バッターに対してやってはいけないことがあります。
対峙するバッターへの情報提供
【球児必見! !】打ちたいなら、ピッチャーの癖をまず知るべし!高木豊が語る分析眼とは…?
■投げる球種がバレる
■狙っているコースがバレる
球種については、例えばフォークボールを投げる際に明らかにボールを挟み込むしぐさを見せることであったり、投げる球種ごとに自然と腕を振る角度がストレートを投げる時と異なったりすることなどのことです。また、コースについては、投げるコースに合わせてピッチャープレートに触れる軸足の位置を変えるといったことがあります。
もちろん、これを逆手に取ったり、キャッチャーとの共同作業によりバッターを困惑させることも可能ではあります。
ピッチャーはコントロールこそが最大の武器となる
ただし、当然ながらコンディションによってはコントロールが乱れ調子が悪いこともあります。そのような時であっても、日々の練習で培った制球力があれば精神的な支えとなりますし、大崩れすることも少なくなるはずです。
小手先でボールを置きに行くことなく、常に強く腕を振って投球できるよう練習を重ねてください。
商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。





