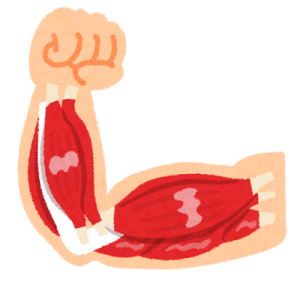
筋肉痛と超回復とは?どんな関係があるのか知っておこう!
筋肉トレーニングや運動をした当日や翌日に、筋肉痛に悩まされることはよくありますよね。今回は筋肉痛と超回復の関係性について詳しく知ってボディメイキングを成功させましょう。筋肉痛や超回復の原理について知りたい人は必見!
Writer
公式ライター Activel_director
筋肉痛と超回復の関係性
筋肉疲労のメカニズム
肉体的筋肉疲労とは
運動中に起こる筋収縮で筋肉への酸素供給が間に合わなくなります。そのためにエネルギー源であるブドウ糖が不完全燃焼を起こすのです。その時に乳酸が残るのですが、筋肉中に蓄積すると筋肉が収縮し、血行が悪くなり、疲労が感じられます。これが一つの説。
もうひとつは傷ついた筋繊維や周辺組織が回復する過程で炎症を起こし、そのときに発生する痛み物質(ヒスタミン、セロトニン、ブラジキニンなど)が筋肉を覆う繊維体、筋膜を刺激するためです。超回復はこちらの説で説明がつきます。ここではこちらの説で話を進めていきます。
精神的筋肉疲労とは
首筋の後ろや背骨の左右、肩甲骨の内側はストレスからくる影響が表れやすい場所です。慢性的にこれらの痛みを感じる場合は、ストレスの原因から突き止めましょう。
筋肉痛と超回復の関係
筋肉痛が強いと超回復の効果は大!
瞬発的に激しい運動をすればするほど筋肉の組織は大きく損傷します。人間の体には壊れたり疲労したりした組織を修復する機能があり、このとき以前の体よりより強固にしようとします。こうして自力でより強くなろうとするのが筋肉の超回復なのですが、損傷が大きければ大きいほど、つまり筋肉痛が強ければ強いほど超回復もそれに負けじと大きくなります。
筋肉痛の回復と超回復の目安
また、筋肉の部位別によって超回復の時間も異なります。たとえば、腹直筋(ふくちょくきん)や下腿三頭筋(かたいさんとうきん、ふくらはぎ)は回復するのに24時間で大丈夫です。鍛えた部位は基本的にトレーニング後から2日あけるのが原則ですが、なるべく毎日に近い形で筋トレをしたかったり、そうして毎日の代謝を上げることが目的であれば部位を分けてトレーニングすることもまた一つの方法です。
効果的に筋肉痛を和らげ超回復を促進するには?
超回復の大前提
まず栄養です。基本的にタンパク質、糖質、ビタミン、ミネラルの摂取が大事なのですが、このうちもっと気を付けたいのはタンパク質です。一般の成人(筋肉トレーニングをしていない人)の一日に必要なタンパク質の摂取量は70gですが、筋トレをしている人はその倍以上、つまり140~210g必要になります。普通の食事だけでは到底到達するのが難しいので、プロテインを使用するわけですね。
休養については上で述べたとおり、超回復の期間は筋肉を休養させておくのが重要で、この期間に筋肥大が起こるんですね。
休養の方法
アフターケアとしてストレッチをして、硬く張った筋肉を柔らかくすることも大切です。筋肉をほぐし血液の循環を良くすることで、酸素や栄養素を供給して老廃物を流し捨て、超回復を助けます。
また、クールダウンも超回復に効果的な方法で、筋肉疲労の回復に良いです。運動直後の筋肉にたまる血液を心臓に戻して貧血状態を予防するとともに、運動中に生じた疲労物質を筋肉から除去する働きがあります。
うまく自分で取り入れて効率よく筋肉を休ませましょう!
筋肉痛についての疑問
筋肉痛の時に筋トレをしても良いか?
筋肉痛がないと筋トレの意味がない?
しかし、筋肉痛がないからといって効果が出ていないわけではありません。それは筋肉が発達している証拠ですし、超回復は筋肉痛に関係なく起こります。筋肉トレーニングにおいて疲労は必要ですが、筋肉痛は必ずしも必要ということはありません。十分に楽になってきたら重量を上げればよいのです。
まとめ
自分が疑問になった情報収集は怠らないことはもちろんですが、結局は自分が体感し気づくことができれば何も問題はありません。自分の体と対話することも忘れないようにしましょう。
商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。













